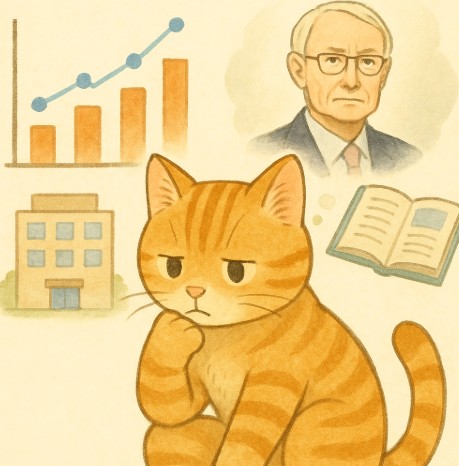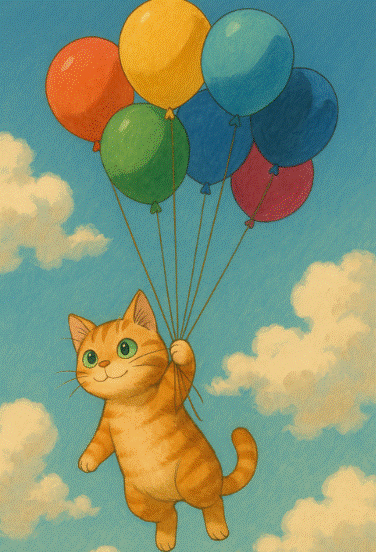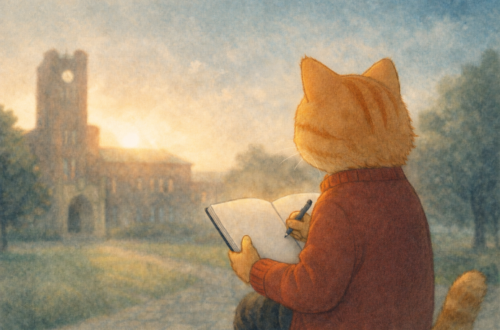社会人MBAの学びの中で、私がもっとも苦戦しているのが「研究論文」です。授業や課題は何とかこなせても、論文執筆は「そもそも研究とは何か?」という根本から迷ってしまう。
まだ完成には程遠いのですが、その過程での気づきや学びを共有したいと思います。
卒論との違い:MBA論文に求められること
大学時代の卒論は、知識整理に近いものでした。しかしMBAでは、理論的意義(アカデミックな意味)と実務的意義(ビジネスや社会にどう役立つのか)が同時に求められます。
単なる感想文やレポートではなく、先行研究に基づき、論理的に問いを立てて検証していくことが必要になります。
テーマが定まらない苦しみ
入学時からテーマを明確に持っている人もいますが、私はそうではありませんでした。講義やセミナーを受けながらアイデアが出るだろうと楽観していたものの、結果として「キーワードは浮かぶけれど、テーマにまとまらない」という状態が長く続きました。
特にリサーチクエスチョン(研究課題)を定めるのには苦労し、何十個も候補を書いては消すことを繰り返しました。
研究は「巨人の肩に立つ」営み
Google Scholarのトップにある「Stand on the shoulders of giants」という言葉の通り、研究は先人の知恵の積み重ねです。大発見を目指す必要はなく、小さな新しい視点や、実務への応用で十分に価値があります。
論文執筆を助けてくれた2冊の本
1. 『論文の教室 レポートから卒論まで』(戸田山和久 著)
この本は、論文の基礎を一から解説してくれる「教科書」です。
特に印象に残ったのは、パラグラフライティング(段落ごとに主張を明確にする)と論証の組み立て方。MBA論文のように論理展開が問われる文章では、この基本を意識するだけで大きく変わると感じました。
新版 論文の教室 レポートから卒論まで (NHKブックス) | 戸田山 和久 |本 | 通販 | Amazon
2. 『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』(阿部幸大 著)
こちらはさらにアカデミックな視点から「研究の問いをどう立てるか」「主張をどう論証するか」に踏み込んでいます。
特に「アーギュメント(主張)をつくる」ことに焦点を当てており、MBA論文で欠かせないリサーチクエスチョンを研ぎ澄ませる作業に直結する内容でした。
まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書 | 阿部幸大 |本 | 通販 | Amazon
この2冊を読んで感じたのは、論文は「思いつきを文章にまとめる」のではなく、問い → 主張 → 論証 → 結論という筋道をきちんと設計して積み上げていく作業だということです。
書けない自分から始める
それでも、いざ書こうとすると「これでいいのか」と迷いが続きます。集めた研究のキーワードを集めては崩し、また読み直して……の繰り返しです。
でも、それが研究のプロセスなのだと思います。小さな一歩の積み重ねが、やがて論文という形になる。
まとめ✍
社会人MBAの論文執筆は、知識や時間だけではなく「研究する姿勢」そのものが問われる挑戦です。
今回紹介した2冊の本は、そんな挑戦を支えてくれる大きな助けになりました。
- 『論文の教室』は論文の「型」を学ぶ教室
- 『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』は研究の「思考法」を鍛える教科書
私自身まだ道半ばですが、同じように苦戦している方がいたら、この2冊を手にとりつつ、自分のリサーチクエスチョンを探してみてください。